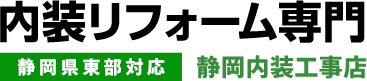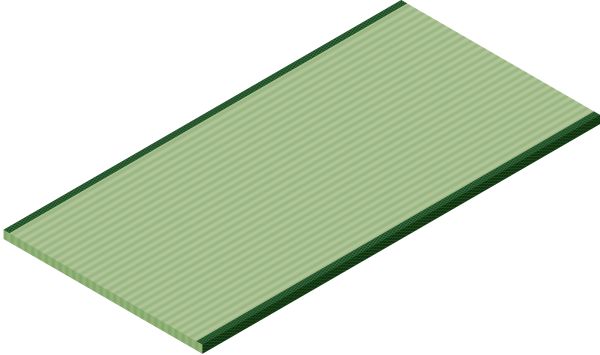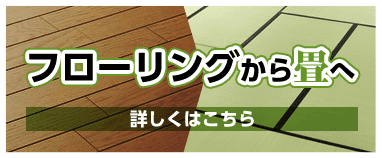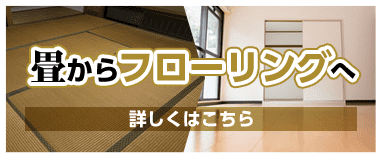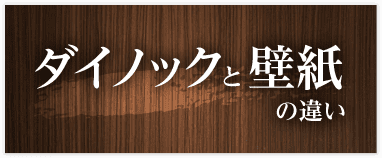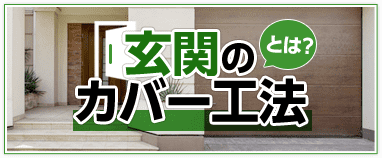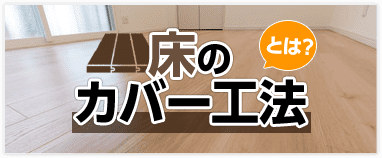「畳の表替えって何?」「どのタイミングでやるべき?」そんな疑問をお持ちではありませんか?
畳の表替えをおこなうと、和室の雰囲気が一新され、快適な住環境を維持できます。
しかし、表替えの知識がないと適切なタイミングを逃して畳が傷み、修繕費が高額になる可能性が高いです。
この記事では、表替えのメリット・デメリット、適切な時期、業者の選び方などを詳しく解説します。
畳の寿命を延ばし、美しい和の空間を保つためのポイントを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
表替えとは

畳の表替えとは、畳の芯材である「畳床(たたみどこ)」をそのままにして、表面の「畳表(たたみおもて)」を新しく交換する作業を指します。
これにより、畳全体が新品同様の見た目と感触に生まれ変わります。
また畳の表替えは、一般的に5年から10年に一度の頻度でおこなうのが理想的です。
ただし、使用頻度や設置環境によって劣化のスピードは異なるため、畳の変色や毛羽立ち、ささくれが目立ち始めたら、表替えを検討するとよいでしょう。
表替えのメリット
表替えの主なメリットの一つは、費用対効果の高さです。
畳床を再利用するため、新調するよりもコストを抑えつつ、見た目と機能性を向上できます。
また、短時間での施工が可能な点も利点です。
畳床を交換しないため作業時間が短縮され、日常生活への影響を最小限に抑えられます。
通常、表替えは1日で完了するため、忙しい家庭でもスムーズに対応できます。
表替えのデメリット
畳の表替えにはメリットがある一方で、畳床の劣化には対応できないというデメリットがあります。
表替えは、畳表(たたみおもて)を新しくするだけの作業であり、畳床(たたみどこ)の状態はそのままです。
そのため、畳床が劣化している場合、表面だけを新しくしても耐久性や快適性が十分に向上しない可能性があります。
畳の構造
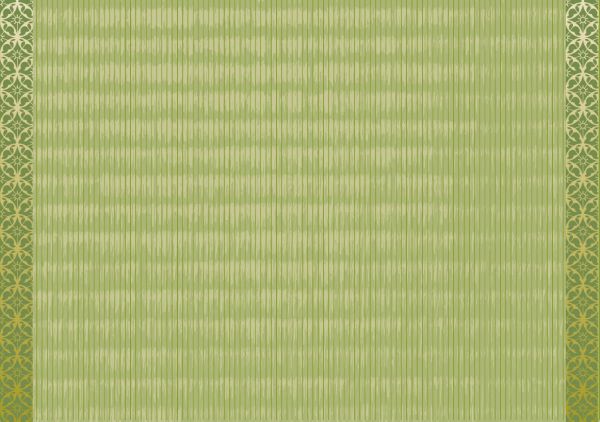
畳は主に以下の3つの部分で構成されています。
・畳床(たたみどこ)
・畳表(たたみおもて)
・畳縁(たたみべり)
畳床(たたみどこ)
畳床は畳の芯となる部分で、畳の厚みやクッション性を決定する部分です。
従来は藁(わら)を重ねるのが一般的でしたが、近年ではインシュレーションボードやポリスチレンフォームなどの新素材も使用されています。
これらの新素材は、軽量で断熱性や耐湿性に優れているといった特徴があります。
畳表(たたみおもて)
畳表は畳の表面部分で、直接肌に触れる部分です。
伝統的なイ草を使用すると、香りや質感が日本の風情を感じやすいです。
しかし、イ草は水分を吸収しやすく、シミや汚れが付きやすいというデメリットもあります。
これらの欠点を補うため、近年では耐久性やメンテナンス性が向上している和紙や樹脂を素材とした畳表も登場しています。
畳縁(たたみべり)
畳縁は畳の縁に付けられる布で、装飾性と補強の役割を持ちます。
伝統的には綿や絹が使用されていましたが、現在では化学繊維の畳縁が主流となり、無地や柄など多彩なデザインが揃っています。
例えば、格式のある和室では家紋入りの畳縁が使われたり、モダンなインテリアにはシンプルな無地や幾何学模様の畳縁が選ばれたりする場合が多いです。
畳の表替えはどこに依頼する?
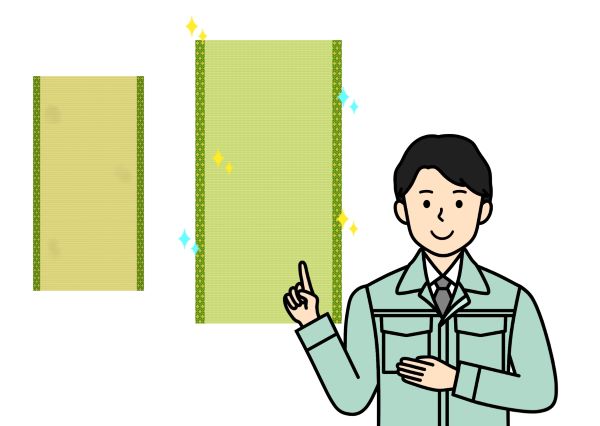
畳の表替えを検討する際、依頼先として以下の選択肢があります。
・ホームセンター
・畳店
・リフォーム会社
ホームセンター
ホームセンターでは、手軽に畳の表替えサービスを利用できます。
価格が比較的安価である場合が多く、他のリフォーム商品と合わせて相談できる利点があります。
ただし、専門的な知識や技術が必要な場合、対応が限られるため注意が必要です。
畳店
畳店は、畳の専門家が在籍しているのが特徴です。
地域密着型の店舗が多いため、迅速な対応やアフターサービスが期待できます。
また、イ草の品質や畳表の種類などについて詳しい説明を受けられるため、適切な選択が可能です。
ただし、費用がやや高めになりやすいので、相見積もりをとって比較する必要があります。
リフォーム会社
リフォーム会社に依頼すると、畳の表替えだけでなく、部屋全体のリフォームと合わせて施工できるメリットがあります。
特に畳の表替えと一緒に襖(ふすま)や障子の張り替え、壁紙のリフォームを依頼すれば、個別に業者を手配する手間が省け、トータルで統一感のある和室に仕上げられます。
ただし、リフォーム会社によっては畳の種類が限られる場合があり、デザインや素材にこだわる場合は畳専門店に相談するのがよいでしょう。
当社の畳リフォームについては「畳張替え」をご覧ください。
畳を長持ちさせる方法

畳を長持ちさせるためには、日常的なメンテナンスが重要です。
適切な手入れをおこなうと、畳の寿命を延ばし、快適な住環境を保てるようになります。
定期的な掃除
畳を長持ちさせるには、定期的な掃除が必要です。
畳は湿気を吸収しやすく、汚れがたまりやすい素材です。
適切な掃除をおこなわないと、ダニやカビが発生し、衛生面や耐久性に悪影響を与えます。
例えば、掃除機をかける際は、週に2〜3回の頻度で畳の目に沿ってゆっくりと動かすと効果的です。
また、乾いた布で軽く拭くと、畳表の汚れを防げるようになります。
特に、畳に液体をこぼした場合はすぐに乾いた布で吸い取り、その後固く絞った布で軽く拭くとシミを防げます。
ただし、洗剤を使用すると畳の変色や劣化を招く場合があるため、避けたほうがよいでしょう。
こまめな換気
畳は湿気を吸収しやすいため、室内の換気が必要です。
特に梅雨の時期や雨の日が続いた後は、窓を開けて風を通し、湿気を逃がすようにしましょう。
また、エアコンの除湿機能を活用するのも効果的です。
例えば、朝起きたら窓を開け5〜10分程度空気を入れ替える習慣をつけると、湿気がこもりにくくなります。
雨の日が続いた場合は、扇風機やサーキュレーターを使って室内の空気を循環させるとよいでしょう。
畳干しをする
定期的に畳を干すと、湿気を取り除き、ダニやカビの発生を防げるようになります。
例えば、晴れた日には畳を少し持ち上げ、下に空き缶やブロックを置いて空気を通す「畳上げ」をおこなうと、湿気がこもりにくいです。
また、押し入れに畳を収納する場合は、新聞紙を敷いて湿気を吸収させるとカビの発生を防げます。
自分で畳干しをするのが難しい場合は、畳専用の乾燥サービスを利用すると手間なくダニやカビ対策ができるため便利です。
湿気の多い地域では、年に1〜2回の畳干しをおこなうとよいでしょう。
まとめ
畳の表替えは部屋の雰囲気を一新し、快適な住環境を維持するための重要なメンテナンス方法です。
優良業者を選ぶには実績や口コミを確認し、見積もりの内訳が明確な業者を選ぶ必要があります。
また日々の掃除や換気、畳干しをおこなうと、畳の寿命を延ばしより長く快適に使用できます。
畳の状態を適切に管理し、美しい和の空間を保ちましょう。
*K*
お見積りやご相談などございましたら、お気軽に静岡内装工事店へお問い合わせください。
静岡県焼津市・藤枝市・島田市で内装リフォームのことなら、静岡内装工事店へお気軽にご相談ください。