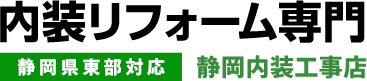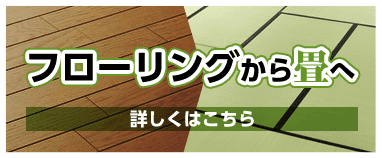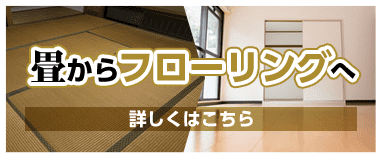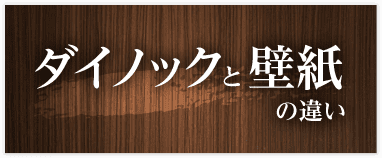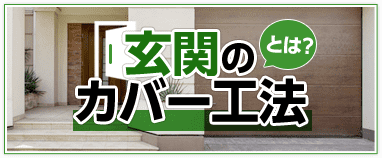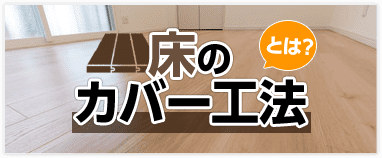畳は約1,300年以上の歴史があり、現在でも旅館や茶室だけでなく、住宅の和室インテリアとしても広く使われています。
しかし、畳は適切に管理しないとカビが発生しやすく、アレルギーや喘息などの健康リスクを高める可能性もあります。
そこで本記事では、畳にカビが発生する原因を解説し、快適な住環境を守るためのポイントを紹介します。
畳にカビが生える主な原因とは?

畳にカビが発生する原因には、日本特有の高湿度な気候と現代の住宅環境が大きく影響しています。
昔の住宅は主に木造で通気性が良く、高床式や襖(ふすま)など風通しが良い構造になっていました。
しかし、現代では冷暖房の効率を高めるために気密性が高くなったことで、エアコンを使用する際に窓を閉めっぱなしにすることが多くなり、湿気がこもりやすい環境となっています。
このような湿気がこもりやすく換気が十分でない住宅ではカビが発生しやすく、住宅の劣化を早める要因となります。
特に、湿度が70%を超え温度が20~30℃の範囲になると、カビの繁殖が加速します。
また、住宅の立地条件によってもカビのリスクは変わります。
例えば、川や湖の近くに建てられた住宅は年間を通じて湿度が高いため、畳がカビやすい傾向があります。
さらに、日当たりが悪く、風通しの悪い部屋では湿気がこもりやすく、カビが発生するリスクが高くなります。
そのため、畳のカビを予防するためには住宅全体の湿気管理が不可欠です。
畳のカビを未然に防ぐには?

畳は、湿気を吸いやすくカビが発生しやすいという難点があります。
カビを防ぐには湿度管理・換気・掃除の3つが重要ですが、どれだけ対策をしても完全に防ぐのは難しい場合があります。
ここでは、カビの効果的な対策について詳しく解説します。
①室内の湿度を40~60%にコントロール
畳のカビは湿度が高い環境で発生しやすいため、まずは湿度を管理することが大切です。
具体的には、以下の方法で湿度をコントロールできます。
・除湿機やエアコンの除湿機能を活用する
・窓を開けて換気し湿気を外に逃がす
・晴れた日に畳を上げて風を通す
②畳の下に湿気を溜めない工夫をする
湿気がこもるとカビが発生しやすいため、畳の下の通気性を良くすることが大切です。
以下のポイントを押さえることで、湿気対策が可能になります。
・すのこを敷いて空間を作る
・家具を直接置かないようにする
・家具を置く場合は脚付きのものを選び隙間を作る
③掃除をこまめにする
カビはホコリや汚れを栄養源にして増殖するため、定期的な掃除が必要です。
・掃除機をかけてホコリや皮脂汚れを除去する
・固く絞った雑巾で畳を拭き、乾拭きをして水分をしっかり取り除く
畳のカビ対策
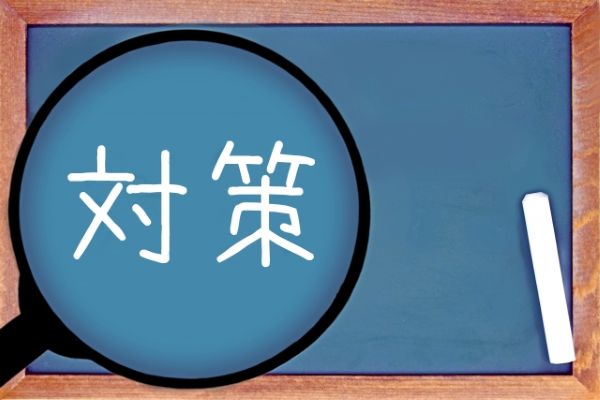
畳のカビを防ぐためには、湿度管理・換気の工夫・日々の掃除が不可欠です。
また、湿度が高くなる季節だけ対策をするのではなく、年間を通じて住環境を整えることが重要です。
特に高気密住宅では換気が不足しがちなため、畳のカビ対策として畳の素材選びや住宅全体の湿気対策をおこなうことが必要です。
安心して過ごせる住環境を維持するためのカビ対策について詳しく解説します。
畳の素材選びによるカビ対策
近年、カビの発生を防ぐために、従来のい草畳に代わるさまざまな素材が登場しています。
新築やリフォームの際に、これらのカビに強い畳を選ぶことで、長期的なカビ対策が可能になります。
・い草畳:伝統的な畳の素材で、独特の香りには安心感やリラックス効果があります。また調湿効果があり、肌触りも良いのも特徴です。ただし、カビが発生しやすいため湿気対策が必要です。
・和紙畳:和紙を細く加工しコーティングした畳です。モダンな和室で採用されることが多く、カラーバリエーションが豊富でデザイン性に優れています。い草に比べて耐久性が高く、カビが発生しにくい特徴があります。ただし、い草の香りが楽しめず、調湿効果は期待できません。
・樹脂畳:ポリプロピレンなどの樹脂素材を使用した畳です。ペットを飼っている家庭や、い草に対するアレルギーがある方に適しています。傷がつきにくくカビの発生も抑えられるため、保守性に優れています。
・琉球畳:正方形の形状をした畳で、七島藺(しちとうい)という植物を使用しています。もともとは柔道の畳として使用されていましたが、近年ではデザイン性が評価され、インスタやSNS等でもインテリアの一部として人気を集めています。耐久性は高いものの、一般的ない草畳と同様にカビ対策が必要です。
住宅における畳のカビ対策
畳のカビが発生する大きな原因の一つは、住宅全体の換気不足です。
現代の住宅は気密性が高く、外気の流入が制限されるため、湿気がこもりやすい環境になりがちです。
特に畳は湿気を吸収しやすく、適切な換気がおこなわれていないとカビが発生しやすくなります。
そのため、住宅の換気システムを整え、湿気対策を強化することが畳のカビ予防につながります。
・24時間換気システムの導入:シックハウス症候群の予防を目的として、2003年の建築基準法改正により、すべての建築物に設置が義務付けられました。
室内の空気を常に循環させ、湿気を逃がす役割があります。特に冬季は冷気が入るため止める人もいますが、換気のためには常時稼働させることが推奨されます。
・床下換気扇の活用:畳のカビは、床下の湿気が原因で発生することが多く、特に梅雨や夏場は床下の湿度が高まりやすくなります。床下換気扇を導入することで、湿気を効率よく排出し、カビの発生を抑えることができます。
・調湿効果のある建材を活用:調湿機能のある建材を活用することで、畳のカビを防ぐことが可能です。例えば、珪藻土(けいそうど)の壁材や、吸湿・放湿性能を備えた壁紙を採用することで、室内の湿度を適切にコントロールできます。
まとめ
畳はその快適さや美しさから多くの人に愛されています。
しかし、現代の住宅環境では湿気がこもりやすく、適切な対策を講じなければカビが発生しやすくなります。
日常の管理に加え、畳の種類の選定や住宅の換気設備の改善をおこなうことで、より効果的なカビ対策が可能になります。
適切な対策を実施し、健康で快適な住環境を維持しましょう。
*K*
お見積りやご相談などございましたら、お気軽に静岡内装工事店へお問い合わせください。
静岡県焼津市・藤枝市・島田市で内装リフォームのことなら、静岡内装工事店へお気軽にご相談ください。